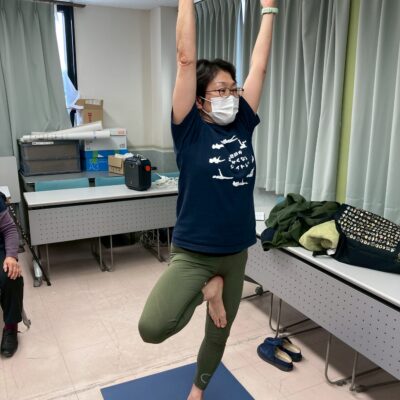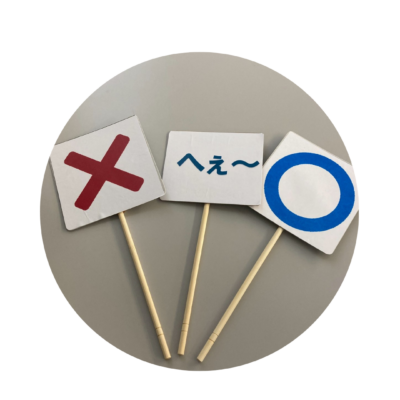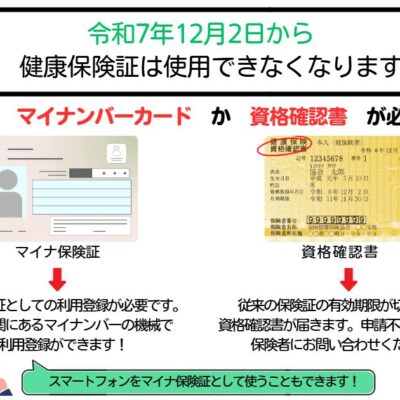7月3日(木)暮らしの保健室を開催しました。今回の講師は長野県認知症介護指導者の資格も持つ 増井茂樹さん です。
テーマは「いっしょにあるく」 認知症についてわかりやすく、楽しくお話してくださいました。

「認知症」と聞いてどんなことをイメージされますか?との質問に、「ご飯を食べたことを忘れる」「外へ出て行って歩き回る」などの答えが参加者の方から出ました。実は、その行動には理由や目的がある、ということを具体的な例を挙げてお話してくださいました。
今では聞きなれた「徘徊」という言葉。辞書で調べると「目的もなく歩き回ったりすること」とあります。でも、目的はあるんです!施設から「帰りたい!」という方。「子供が帰ってくるから」「夕食の準備しなきゃ」など、その方が今まで歩んでこられた人生によって、帰りたい理由は様々です。どんな行動も、その方なりの理由があります。でもこちらが「理解」できるかどうかは「別」です。
政府から「新しい認知症観」というものが出されました。
「新しい認知症観」とは、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という考え方のことです。
これから65歳以上の人が認知症になっていく割合は「3人に1人」だそうです。これを聞くとみなさん心配になりますよね?
だからこそ「新しい認知症観」を私たちが正しく持つことが大切だと、増井さんはおっしゃいました。
次に、増井さんも制作に携わった「いっしょにあるく」という絵本の読み聞かせをしてくださいました。
「いっしょにあるく」は実際に認知症になった方にお話を聞いて、増井さんをはじめ、介護に関わるたくさんの人が思いを込めて作った絵本です。

認知症の方も記憶がなくなったり、今までできていたことができなくなったりすると、不安で焦って、それを追及されると怒ったりしてしまうことがあります。
そんな時、私たちがイライラしたりイヤな顔をすると、その表情を認知症の方も見て覚えています。
「不安だから必死になって怒っているように見えるだけ」だと、私たちがわかっていることが、お互いほっとすることにもなります。
認知症の方だけでなく、病気や障害があっても「自分で決めたい」という思いは誰でも持っています。
本音は手を貸してもらいたいけど、申し訳ない、恥ずかしいという気持ちがあると、なかなか言い出せないこともあります。
こちらが決めつけて「わかるよね?!」と言うと答えられなくなるけど、「〇〇しませんか?」と相手の意思を話してもらう聞き方をすると答えやすい、というお話は、育児にも使える!と個人的に思いました。声のかけ方ひとつで変わることがたくさんあるのだなと感じました。
また、介護をしているご家族の方にも、たまには隣に座ってきれいな月を一緒に見たりするひとときがあると、ふっと肩の力が抜けるというお話もしてくださり、認知症の方、介護する方、関わる方、いろんな立場があるけど、寄り添って一緒に過ごしましょう、というやさしいお話でした。
お話の後、「認知症にならないためにはどうしたらいいの?」「治す方法はあるの?」など質問が飛び交いました。
今は「こうすれば認知症になりません」という答えはないそうです。
そこでやはり大切になるのが「新しい認知症観」です。そういう増井さんのお話を、みなさん真剣に聞かれていて、「また聞きたい」という声もいただきました。

今回の学びで、誰もが正しく優しく認知症と付き合っていけるようになればいいなと思いました。
※お知らせ※
次回から 第3水曜日 14:00~15:00 に開催曜日が変更になります。
会場もけやき薬局3階になります。
次回は 8月20日(水) テーマは「一生自分の足で歩く(仮)」です。
引き続きご参加をお待ちしております!